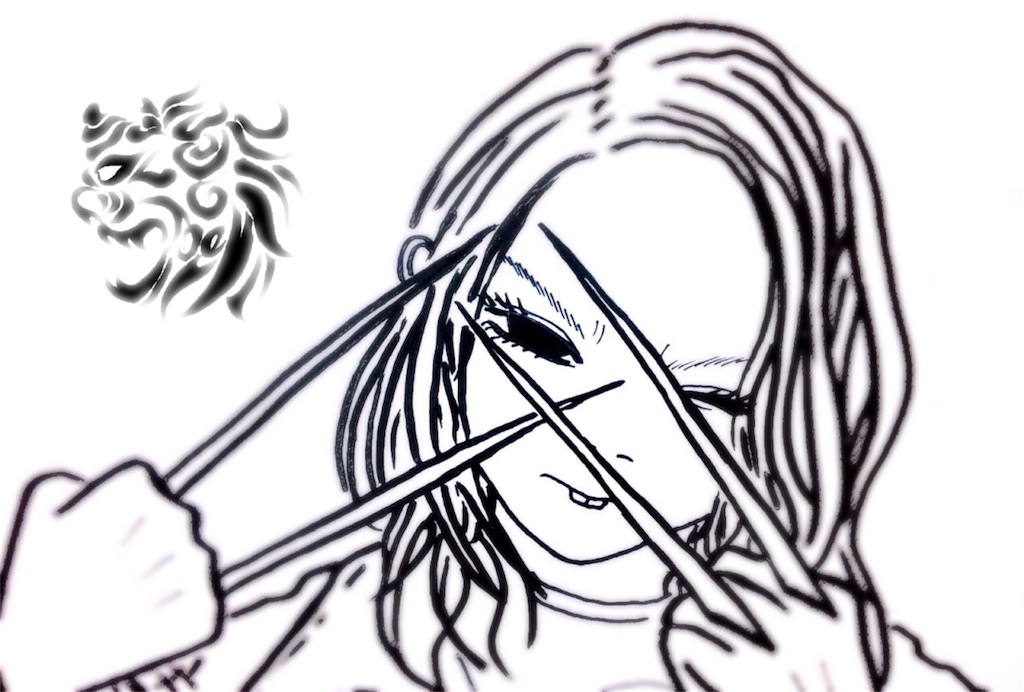sakamoto-the-barbarian.hatenablog.com
我が文芸部の部室のドアには、星のカービィのシールが貼られている。ボロボロになって腐敗の進んだゾンビみたいなやつで、一年のころに先輩に聞いたところ、先輩の先輩の先輩の代からずっとあったものらしい。毎日のように目にしていたはずなのだ。なのに改めて目の前に立ったとき、僕はそいつと偶然出くわしてしまったような気持ちになった。廊下では吹奏楽部の他に軽音楽部の練習する音が響き渡っていて、立ち止まればビリビリと肌が振動するのがわかるが、その中でまたしても僕はぼーっとしている。なにかを掴みそこねている感覚がずっと付きまとっていて、もどかしい。億劫だった。
不思議。
重いドアなので表面に肩を押し当てながらノブをひねりかけた僕だが、隙間ができるか否かのその瞬間、扉の奥から微かに人の声が聞こえたかと思うと、無意識のうちに身体を硬直させ、耳をすませていた。なんだか盛り上がっている。会話? そう思ったけど違う。なにかを歌っているのだ。僕はその邪魔をしたくなくて、ドアを開ける次のタイミングを待っていて、せっかくだからとドアに両手と耳を当ててみる。この声はなっちゃんのものか? 桐子もいるのかもしれない。手拍子まで聞こえる気がした。なにかの合唱曲か歌謡曲っぽいメロディが続き、やがてわー! と声が沸くので、僕はそのどさくさにまぎれて勢いよくドアを開ける。
八重子教諭が卒倒しそうなほどの熱気が漏れ出てきて、いっきに僕の前半分を湿らせるように撫でていった。
そこでようやく気づいた。
僕はちょっとビビっているのだ。
部室には予想した通りなっちゃんと桐子、その他に久留米と、なんと照本肇までいて、彼は部室に常備してある安物のサングラスをかけ、カーディガンをディレクター巻きしている。坂本の姿はなかった。僕がなにかをしゃべりだすよりも先に「なんだよその格好」と言ってきたのは久留米だった。相も変わらず真っ黒で動きの乏しい目をしている。声の抑揚も乏しいが、合唱の直後だからか、どことなく紅潮しているようにも見える。
照本肇がサングラスを外しながら「まだ見つかってないのか!」と満面の笑みを見せるなか、僕は腰に手を当て、俯き、考える。学ランもない。肝心の坂本もいない。全身に力が入っているので妙に緊張しているような気分だったが、単純に寒いのだった。
「ほらほら、ドア」
桐子に促されるまま扉を閉め、しばらくその場に立ち尽くしていた。じゃあ僕はこれからどうするべきなんだっけ?
「泣けてきた」となっちゃんがなんらかの文脈で突然つぶやいた。奇遇にも僕もまったく同じことを思っていた。彼女はペンをもち、その尻でおでこをかいている。今日はコンタクトの日だ。
横で落ち着きなく腕を組んだりおろしたりしていた照本が、とつぜん「あ、そうだ」と言い、肩にかけていたカーディガンをするりと外す。
「安藤、これを着たらいいよ」
「え?」
「いいから。からから。学ラン見つかったら返してね」
「でも照本、寒いでしょ?」
「いや。おれには学ランあるし」
「あそうか。ありがたいね。いつまで借りてていいの?」
「どうでもいいよ」と言った、照本は妙にゆったりと笑った。ように見えた。それから「あしたでもいいし」と言う。
明日は土曜だな、と思う僕は合掌した。「あたたかい」。ちなみにこれは加藤が貸してくれたんだ。ほら、知ってる? 二組の、とマフラーを直しながら言うと、照本肇はパン! と顔の前で手を叩くのでちょっとびっくりする。
「もしかしてあのハンサム?」
「たぶん」
「あ、加藤くんのなんだ」となっちゃんがパイプ椅子の背にもたれ、ギュイイイ、と鈍い音を立てた。「厳密には、加藤の妹のだけどね」と僕が言うと、「うおーう。いいね」と久留米。スマホを触っている。「そうそう」と答える僕は改めて照本肇にお礼を言い、「二つの意味で恩に着ます!」と言いながらカーディガンを羽織った。意味があまり伝わらなかったようで一瞬固まった照本は「構いません!」と敬礼。そんな僕らを見てなんだそれ、という顔をしていた桐子だったが、「加藤さんって妹いましたっけ?」と机に肘を立てながら訊ねる。
「そうそう、いるね」
「へー」
「美少女だよ」
「えーうそー。でもぽいぽい。加藤さんも女装似合いそうですもんね。だってほら」
「ん?」
「見た目がこう……なんだっけ。フェ……フェフェフェフェフェ」
「どうしたんだよ」
「フェから始まる言葉」
「フェラチオ」
「死ね」
「わかったフェミニン!」となっちゃんが言うと
「それ! フェミニンな感じありますもんね」
「なるほどね」僕はフェミニンの意味をよく知らなかった。
「なんかね、ユニセックスというか」と桐子が続けるので、僕がひとり笑っていると「下ネタじゃねえよ馬鹿」と彼女。馬鹿は響くぜ。
「学ランもないくせに」
「やめてよ」
「でもあんなもん、ふたつもいらないのにな」と言いながらソファーの久留米が脇によってくれるので、僕は敷き詰めるようにその隣に座る。「ていうか盗まれたかどうかも謎なんだよね。謎が謎を呼ぶ状況ですよ」
「坂本に聞けば?」
という久留米の言葉で僕は思い出す。「ああ、そうそう。それなんだけど、あいつ今日きてないの?」
「きてない」
「そうなんだ」
「きてない」
了解。
一息つこうとの思いは満々なのだけど、空のペットボトルや借りっぱなしの本、落書きだらけのルーズリーフやA4サイズのコピー用紙で埋め尽くされた机の上を眺めていると、渡部先生の声が蘇ってくるので僕はちっとも落ち着かない。掃除か~。掃除もしなきゃならないんだったな~。もしこれで坂本が学ラン持ってなかったらどうすんだ、と僕はどんどん心的ぬかるみにはまっていくのだった。
ずっと考えないようにしていたけど、サッカー部でもないのなら、本当にまだ進路が決まっていない誰かが僕を攻撃していることになってしまう。となると容疑者は三年生の半数以上だ。今夜は眠れなくなるだろう。そうなると日中眠くなる。自習時間に僕がウトウトしていようもんなら、あいつは進路が決まってるからいい気なもんだね、死ねばいいのに、とか思われるんだろうし、そういうのって思っている以上に空気にのって肌を刺してくるものだ。でも明日は土曜日で、あ、よかったよかった、と一瞬僕は思うけど、まだ安心に足るほどではないのだ。たとえ明日が土曜日だとしても、土日の夜ふかしはいつものことで、月曜まで寝不足を引きずる可能性は充分にある。
オナ禁しようかな。
なんて自ら不安がることで免罪符を得ようとしているしみったれた逃避に興醒めした僕だが、とはいえこれまでの抑圧からくる反動を理由に最後の最後で仕返しの意味も込めて意図的にはしゃいで見せるんじゃなかった、と心から思い始める。どう考えたって悪手だった。そんな自分の浅ましさにはもう涙すら出ないが、ひどく思いつめてるかといえば実のところそこまで本気にもなれなくて、もうどんな理由で、犯人がだれであろうとかまわないから、学ランさえ返ってくればそれでいいや、なんて僕は思う。神様。
「そうだ安藤、図書館いって『火の鳥』読む?」
唐突に隣の久留米がそう言うが、うっかり聞き落としてしまったのか、どういう流れかまったくわからないうえに気分でもなかったので、「いまからか」と発したっきり黙っていると「そこまで嫌がられると逆に新鮮だな」と隣から小さく聞こえてくる。まってくれ、嫌ではないんだよ。今じゃないだけで。と口に出せばいいのに、僕は笑うだけでなにも言わない。久留米は「おれひとりで行くわ」と独り言を漏らしたが、特に動き出すこともなくスマホを眺めている。照本が笑うのに続いて桐子が「えーそれはない!」と叫んだ。なにがないのか耳を傾けてみると、「そういや桐子ちゃん久々に部室いるね」となっちゃんが言って、結局新しい話に移る。
「あ、そうですね。練習の順番待ってるんですよ。軽音の」
桐子が言うとなっちゃんが「あー。ねー」と首を傾げる。
「ああ、それでか」
僕がなんの気なしにつぶやくも誰も反応しなかったので、ちょっとびっくりして、ついついひとりで喋り続ける。
「いやほら、みんなで歌ってたじゃん。けっこう長く」
「あれ、なんで知ってるんですか?」
「外まで聞こえてたよ」
「えー! ていうかずっと聴いてたんですか?」
「まあ途中からだけど」
「ドアの前で?」
「そう」
「変質者じゃん」
「遠慮だよ」
「入ってこればよかったのに」となっちゃんが本当にそう思っている感じの口調で言うので、桐子が笑う。僕は腰を浮かせると机の上のティッシュを一枚手に取り、鼻をかんだ。
ブ、ズボー!
で、思い出す。
「あ」
「え?」
「そういやなんか桐子さんに言わなきゃならないことがあったような」と僕が言うと「なんすか」と彼女はみんなの顔を見る。みんなも彼女のことを見て僕を見る。
「いやいや、そう構えることじゃないよ」
「はあ」
「そうそう。最後にまた文集つくるんだよね。これはごめん、もう決定事項なんだけど」
「ん?」
「卒業文集ね」
そう口にした瞬間、隣の久留米と目が合った。なぜか久留米も「え?」という顔をしている。
「まあ、わかりますよ。だってもうそういう時期ですもんね」という桐子は、拍子抜けしたように口角だけを持ち上げる。「でも時期って言ってもそういうのはもっと早く言ったりするもんじゃないんですか?」
「ごめん、一昨日くらいに決めたからさ」
「いやいや、例年の流れってやつがあるんじゃないんですか」
「まさにそうなんだけど、それを思い出したのが一昨日で」
「だったらせめて一昨日の時点で連絡するとか」
ぐうの音もでず。
「安藤さんしっかりしてくださいよ」
なんか今日はそんなことばっかり言われるなあと思っていると、隣の久留米が「あ、くそ」と言ってスマホを自分の腿に放り投げる。「電池切れた」
「充電器あるよ」
「おれも持ってるけどつなぎっぱなしにしてないとすぐ切れる」
「じゃあつなぎっぱなしで使えば」
「このソファーコンセントから遠いんだもん」
「機種変、機種変」
「まあ、四月になる前までには」
黙っていた桐子が急に「あ、てことは後藤先輩も書く?」と言う。なっちゃんはしばらくなにかにペンを走らせたあと、「ん?」と顔を上げて辺りを見回した。そういやなっちゃんはさっきからなにを書いているんだろう。スプリングのいかれたこのソファーからじゃ彼女の手元が見えない。
「なにか書くのかって」照本が改めて伝えてやると「ああ、書く書く。え、書くでしょ?」となっちゃんが僕を見るのでびっくりする。
「あ、おねがいします」
「うん」
「おー! 後藤さんの小説また読めるんだ。超いいじゃん」と桐子。
「え、そう? へへへ。そんなに?」とわざとらしいなっちゃんのテンションに桐子はあえて合わせない。
「わたし後藤さんの書くやつが一番好きかも」
ぎこちなく微笑むなっちゃんは目を細めたまま腰をねじりだした。以前にも、照れると体操を始める癖があると本人から聞いたことがある。
「やばい。がんばろ」
「ところでなに書くとかは決まってます?」
「えー。全然」
よし、ここは部長としてひとこと言わなければ、と思った僕が特に考えずに「過去作の続編書けば?」と提案してみる。そのくせ肝心の名前が出てこない。自分のこういうところが嫌いだ。「例えばあれとか。えっとなんだっけ……ちょっと待ってね」
「『毒婦』のこと?」
「そうそう。あと、もうひとつまえの」
「『でかいちわわ』?」
「あーそれ!」
「続編って、でもそんな話じゃなくない?」
「まあ、あくまで提案なんだし、そっちが決めてよ」
「えー適当」
「これ、みんな間に合うか?」と久留米が固い目元をそのままに笑ったので、「そう思うでしょ? 実は浅野はもう書いてるんだよ」と僕はポケットからルーズリーフの筒を取り出してみせる。照本以外のみんなが漏れる声に各々の感情をのせた。
「出たよ、浅野のやろう。手書きだし」
「あははは」
「やめろやめろ、正しい人を責めるな」と言う僕は僕で、部長のくせしてなにも書いていなければ案もない。言わなくてもいいことは言わなくていい。
「だから桐子さんには急で悪いんだけど、もしストックとかあれば出してほしいんだ。もちろんこれから新しいやつ書いてくれても大歓迎だし」
桐子は椅子の背にもたれて腕を組む。それから首をかしげ、自慢のボブヘアーを揺らしてみせた。いちいち溜めるところが面倒なやつだ。
「がんばります」
「さすが」
「ふふふ。わたしも一応部員ですから」
「ありがとう。軽音部もあるのに」
「あ、そうか桐子ちゃん、忙しくない?」となっちゃんが顔を寄せると、桐子は下唇で上唇を覆い隠す。
「いや全然ですって。わたし受験生じゃないですし」
「でも軽音部の練習はあるんでしょ?」
「あるけど家帰ってから書けばいいじゃないですか」
「ええ、マジで? 過労死しないでよ」と僕が言うと久留米も続く。
「思った。おれには無理」
「まあ、つってもわたし、んな大したもの書かないですもん」
おっ、言ってくれるぜ。僕と久留米が肩をすくめると桐子はそっぽを向いてしまう。僕はその他の連絡事項を思いついた順に口に出す。
「ちなみに小説じゃなくて、詩とかでもいいからね。大歓迎だから」
「ならストックあります。超余裕」
「なんなら日記とかでもいいからね」
「それは書いてないです」
「みんなそう言うんだよ、最初はさ」
「なんにせよ過労死はないっすね。八時間寝れます」
桐子渾身のパンチラインでなっちゃんが吹き出し、それを見て照本も笑う。そのままふたりは互いに互いを見て笑い続け、そんな二人を見て久留米も笑った。
「いや~」と深い溜息をついたのは照本が先で、ヤブカラボウにこう言った。
「おれ正直キミらがなにやってるか知らなかったけど、めちゃくちゃ楽しそうだね」
なのでみんなが黙った。褒められた際のリアクションをきちんと用意することなく生きてきた人ばかりだった。照本にそう言ってもらえたその幸甚と、同時に押し寄せてくる「本当にそうだろうか?」という疑念に混乱している。
一足先にまあいいやという脳内麻薬を分泌させたなっちゃんが、照れを滲ませ「ありがとう」と低い声で笑うと、その声に便乗して久留米も笑った。僕も久留米に倣って顔面を弛緩させながら、それでいて妙な焦りを覚えつつ、ソファーから立ち上がる。
「照本くんってなにかつくったりするの、興味ある?」
「いや、どうなんだろ。考えたこともない。でも楽しそうだなとは思う」
「じゃあ、文芸部、入る?」
口に出した瞬間、心臓が大きく脈打つのを感じた。僕の言葉に照本はちょっとだけ固まって、じろりと目を動かす。
「え?」
「どうかな」
「あ、マジで言ってる?」
ここで久留米が「ふきだまりだけどな」などと言い出さないか、僕は内心不安だった。それは桐子が入部する際に発された一言で、「はい、だいじょうぶです」と答えた桐子は、たまたまそういう煽りを楽しめる人間だっただけかもしれないじゃないか。焦りが僕を饒舌にする。
「超、歓迎。卒業まであとちょっとだけど」
「いいじゃん入っちゃいなよ照本さん」と桐子が拍手をする。「歓迎、歓迎」となっちゃんも続く。「去年入ればよかったのに」と久留米も拍手をするので、照本はいきなり天井を仰ぎ見たかと思うと、強く目をつぶる。そして開く。
「なんだよおまえら! おれだってもっと早く仲間になりたかったぜ!」
胸に込み上げるものが、確かにあった。その熱はついには頬を染め、頭頂部からスポン! と抜けていく。僕は腐っても部長なので、照本と熱くハグを交わし握手する。桐子がスマホを構えているので、僕と照本は握手したまま体を斜めにし、シャッター音を待った。画面を確認してうなずく彼女は、ふいに口をひらく。
「ようこそふきだまりへ!」
あ、おまえふざけんなよという目で僕が桐子を見つめていると、照本は軽やかな口調で言う。
「あ、ごめん、ふきだまりってなに?」
彼がそういう言葉と無縁で良かったし、これからもそうあればいいなと思った。
「気にしないでいいよ。ようこそ照本氏!」
「あは、あははは。よろしくお願いしますです」
「残りちょっとだけど思い出たくさんつくろうね」
「つくるぜマジで~。あ、てことはおれもなにか書いたほうがいいのかな?」
真剣な目で尋ねる照本。ああ、この瞳をごらんなさい。僕は久留米にそう言ってやりたかった。
「そうだね。小説に限定せず、エッセイでも詩でもなんでもいいよ。一番大事なことは、照本氏の思いを表現するってことだから。なんにせよ、気を張らず、遣わず、楽しんで書いてよ」
「おお……」
照本は意を決した様子で喉を鳴らしたあと、小さな声を絞り出した。
「実はおれ日記書いてんだよね」
日は暮れかけていた。
あと十分もしないうちに夜に飲まれてしまうそんな気配が窓から忍び込んできている。照本に過去の文集一式を渡していると、不意にドアがノックされる。あれ、いまなんか音した? とみんなで固まっていると、ドアが勝手に開き、その隙間から知らない女子が顔をのぞかせる。
「失礼します。島崎さん、います?」
「あ、はいはい」と桐子が応えると、その女子は「もうちょっとで部室空くよ」と言ったあと、「失礼しました」と静かにドアを閉めた。視線を移せば、桐子がその細い腕に荷物を次々とかけている。
「じゃあわたし行ってきますね。ありがとうございました」
誰もなにも言わなかったが、一人残らず立ち上がっていた。我が校きってのジェントルパーソンたち。桐子は最後のカバンを肩にかけると「先輩たちの新作、楽しみにしてますから」と部室内のみんなに向けて言った。そんなこと言われたのは初めてだった。桐子は人の作品に本気で蹴りを入れられる人間だったし、僕も何度か痛い目を見ていたので、どちらかといえば、みんなを身構えさせることが多かったのだ。
例えば僕が去年の文化祭用の文集に載せた『てんてこ舞のすっとこどっ恋』は、ウラジミール・ソローキンの短編集『愛』の真似をして変なことをやりたい一心で書き殴った魂なき一作で、何行にも渡る単語の羅列や三点リーダの多様を用いて主人公「舞」の恋煩いを描いたのち、脈略のない猟銃自殺で幕を閉じるだけの短編だったのだけど、自分でも三度読み返すのが限界で、普段はもっぱら忘れて過ごしていたというのに、後日部室で鉢合わせた桐子が
「なんか、そう、あれはなんでしょうね。『おふざけ』だけで『遊び』はなかった感じでしたね。いや、わかんないですけど。でもふざけて書くのって正直誰にでもできるじゃないですか。もっと適切に言うと『おどけ』っていうんですか? まあいいんですけど、今度はちゃんと『おどけ』とか『おふざけ』を『遊び』にまで昇華させてるやつか、それかもう本気で、安藤先輩の強く思っていること、感じてることをてらいなく注ぎ込んだ、熱とにおいに溢れたやつを読みたいですよね」
と言ってきて、僕はまずショックで壁まで吹っ飛んだ。というのはもちろん心象表現で、実際はソファーに沈み込んだまま目を伏せて「熱とにおい……なるほどね」とつぶやくことしかできなかったのだけど、それ以来自分の得意技であった「猟銃自殺」を封印せざるをえなくなった。
怖くなったのだ。
桐子の揺れるボブヘアーを眺めながら、だからこそ今回はなにを書こうかな、と僕は考える。これまであまりにもぼーっと過ごしていたが、途端にいま考えなきゃならないことが山ほどあるような気がしてならない。いや、なにも考えなくていいときなんてそもそもあったのか? これはやばい状況なのだ。僕は羅列してみる。
学ランを見つけること。
帰って小説を書くこと。
卒業までのこと。
四月までのこと。
四月からのこと。
……。
「あ、そうだ安藤先輩」
ドアの向こうに消えたはずの桐子が、僅かな隙間から上半身だけを覗かせている。
「なに? あ、締切?」
「そうそう。いつですか?」
「そんなに部数刷るわけじゃないし、二月の中旬なんてどうですか。三年生はもう休み入ってるけど」
僕が視線を向けると久留米も肯く。なっちゃんも。照本は「お~中旬か~」と言いながらひとりはにかんでいる。
「了解です。それじゃあ、近々提出します」
「よろしくお願いします。メールでもいいし、おれに直接持ってきてもいいから」
「了解です」
扉が閉まり、僕はみんなの顔を見回して、「というわけだから、よろしくおねがいします」と言った。
それからついでに渡部先生から掃除を命じられたことも伝えた。
「わたしもしようと思ってたの。月曜くらいから」
と机の上を見つめるなっちゃんの手元に広げられている数枚のはがきが目に入った。よく見るとそれは年賀状で、僕は混乱する。
「え、なっちゃんもしかして年賀状書いてた?」
「うん。お返しのやつを」
「一月終わるけど?」
「ね~。もっとはやく書けたらよかったんだけど。進路のこととかでバタバタしてたし」
ああ、そんな感じね。とりあえず肯くと、なっちゃんも肯いた。
照本は過去の文集を捲っていたし、久留米はようやくソファーから離れ、スマホに充電器を挿している。
そんなみんなを見て、いや、厳密にはさっき桐子が椅子から立ち上がって、みんなも立ち上がったそのときから、僕はかすかな立ちくらみに併せて、まどろみのような、意識の中で曖昧にゆらめく部分が気になり始めていた。
そのときの僕はふと強烈に予感していたのだ。
いずれこの瞬間のことを懐かしむ時が訪れることを。
これまでのあらゆる過去にそうしてきたように。
反射的にその直感を誤魔化そうと、無意識に手を伸ばした先には図書館の本がいくつもあって、その一番上がジョン・ミルトンの『失楽園』で、教養をつけようと借りたままとうとう読破できなかったなと思う僕はその返却日がとっくに過ぎていることにも気づく。ほかに積まれている本も、坂本とか久留米とか浅野とか加藤とかなっちゃんとか桐子とかが適当に借りてきたまま放置しているもので、いい加減返却しなきゃ、図書室の舞先生は絶対僕らのことをブラックリストに入れてるし、なにか言われちゃうんだろうけど、でもこれ以上の先延ばしはもうやめなきゃならない。部室のすみに転がっていたダンボールを手に取った僕は、その中に一冊ずつ本を入れていく。
「あ、返しに行くの?」となっちゃんが言う。僕は彼女の手元に広げられた年賀状のお返しの中に、自分宛てのものがあることがちょっと嬉しい。
「わたしが返しとこうか」
「いいよ。いつもこういうの、なっちゃんやってくれてるじゃん。おれ教室にかばん取りに行くし、ついでだから」
「あ、じゃあおれも途中まで行こうかな」と照本が言った。今日はもうそのまま帰るつもりらしい。照本は僕の抱えるダンボールを指さし、持とうか? と言ってくれる。僕はもちろん遠慮した。久留米は再びソファーに沈んだあと、二人いれば十分でしょ、とつぶやく。いやおまえさっき『火の鳥』読みに行こうとか言ってたじゃねえかよ。でもこういうとき、久留米は本当についてこない。テスト前に「全然勉強してねえわ」と言って、後日赤点をとった問題用紙を堂々掲げるような男なのだ。
「よろしくな」
そんな久留米になっちゃんが笑う。
陽はとっくに沈んでいて、夜を背にした窓に部室の様子が鮮明に映っていた。
浅野の原稿の最後の一枚には「あとがき」と称された文章が載っていた。三年間の活動に対する感慨から始まり、糧となったもの、反省点、今後の目標などが抜かりなく記されていた。それを読み、さすがは読書感想文で外したことのない男だ、と僕は思うのだが、最後の最後で出てくる一文だけはやや趣が違った。
そこにはこう書いてある。
『これからもくだらないこと大袈裟にしながらクソッたれな大人になっていこうぜ』
図書館前まで付き合ってくれた照本に僕は礼を言う。
カーディガンと、部員になってくれたことも含めて。照本は改めて「学ラン見つかるといいな」と言ってくれる。
「見つけてみせるぜ。卒業式で恥かきたくないし」
「あーそうか。卒業式か。ほんとすぐだな」
「はやいよな」
「あ、そういや安藤。今日はもう塾いかないでしょ?」
「あー。うん。でも明日は行こうかな。またマックで……そうだよマックで小説書こうぜ」
「お! おー! それいいな!」
「じゃあ来週はそれだから!」わははと笑う僕と照本のスキンシップはエスカレートする。肩、腕、腰、腿、お尻。
「それじゃあおれは帰るぜ! 今日はマジでありがとう、安藤部長」
「よせやい、こちらこそありがとうだぜ」
気をつけてな、と手を掲げる僕に、照本は角を曲がるまで独特なステップを踏み続けてみせた。
「なにそれ!」
大声でたずねると、角の向こうから「オリジナル!」という彼の声が響いてきた。
僕は足元に置いたダンボールを再び抱えて図書室へと入っていく。
舞先生がカウンターの中でパソコンを打っている。目が合うと、その太めの眉が持ち上がった。
カウンターにダンボールを載せ、すみませんが……と事情を説明する僕に、舞先生は「ちょっと部長さん、頼みますよ」と苦笑してみせ、本を一冊ずつ取り出してはバーコードを読み取っていく。
「あ、『失楽園』ある。これちゃんと読んだ?」
「一応、冒頭くらいは」
「えー? 面白いのに」
「渡辺淳一の方は読みましたけど」
「ははは。どっちも安藤くんくらいじゃない? 借りてるの」
思っていたよりも怒られなかったことに安心している自分がいた。でもこれじゃいかんと最後に改めて「申し訳ありませんでした」と頭を下げる。舞先生は「許しません」と断言した。
「今後はちゃんと返すなり延長手続きするなりしにきなさい」
「はい」
「そんな安藤くんももう卒業か」
「そうなんですよ」
「はやいね」
「そうですね。まだ実感はありません」
「そんなもんだよ。もう文集作んないの?」
「あ、作ります。これからなんですけど」
「えーこれからは遅くない? 間に合う?」
「それはもうご心配なく。みんな優秀なんで」
「ははは。そういや安藤くん、大学決まったんだってね」
「そうですね。おかげさまで」
「おめでとう。大学でも書くの?」
「んー……どうですかね。やるやらないってあんまり考えたことないんで」
「へえ、そうなんだ」
「書きたきゃ勝手に書くって感じで、わかんないですけど」
「そっか。登山家みたいだね」
「あ、山があるからのぼる的な?」
「そうそうそう」
「でも確かに書きたいことがあるからってのが一番の理由でしょうね。口じゃ言えないようなことでも、おおらかなんで。話って。どうせ嘘だし」
「先生もそう思う。ある程度はね」
「ある程度?」
「うん。でもまあ、いずれわかるよ。あ、別に不自由なもののことを言ってるんじゃないから、そう身構えないでね。もしかしたらもうとっくに気づいているのかもしれないし。とにかく安藤くんは、まずは楽しむといいよ」
「あ、はい、ありがとうございます」
舞先生の視線が僕の背後に移り、振り返ると本を手にした一年っぽい男子が立っている。僕は「ありがとうございました。失礼します」と頭を下げ、カウンターを離れたが、出口には向かわなかった。なんとなく図書室内を見て回りたかったからだ。
でもすぐにやめる。
並ぶ長机の一番奥に、町山りおの姿を見つけた。
ピュ~イ
僕がダンボールを抱えたまま振り返ると、出口のところに坂本がいて、なぜか中腰で、こいこいと手招きをしている。数年ぶりに会ったみたいな気分だ。僕が近寄ると、「まったくおまえは捜すと見つからないリモコンのような男だよ」と坂本は言った。やつは僕のスマホに大量のラインを飛ばしてその返信を待っていたのだが、充電の持ちが悪いために諦め、たまたま見かけた町山さんを張ることにしたらしい。
「なんでだよ、普通に部室こいよ。確率的に考えても」
「でも町山さん張ってた方が確実だと思って」
「なんだこいつ、馬鹿にしやがって」
僕らはダンボールをバキバキ潰して購買裏の焼却炉まで持っていく。結局坂本は学ランを持っていなかったし、なくなったことも知らなかった。僕はサッカー部の犯行説を話してはみたがたぶんそれはないみたいだし、消去法でおまえが犯人だと思っていたことを正直に伝える。坂本は、おまえの学ランなんていらねえよ、なっちゃんの制服ならネットで出品できるけど、と言った。オタサーの姫は確立されたひとつのブランドらしい。それいいな。お願いしたら卒業後譲ってくれないかな、でもうちはオタサーじゃなくてふきだまりだからな、そうだな、と話す僕らが中庭を歩いていると、図書室の窓から明かりが漏れていて、ついつい視線が誘われる。町山さんの姿が、まだそこにはあった。
「塾行くまではここで勉強してるんだってよ」
と、僕の隣で同じように腰をかがめる坂本が言った。
「は? なんで知ってるんだよ」
「さっき聞いた」
「話したの?」
「ちょっとだけ。おまえ現れるまで暇だから」
「すごいなおまえ」
「おれはそういうのできるタイプだから」
「そういうタイプだもんな」
僕は膝に手を置いたまましばらく黙って、「なに話したの?」と聞いてみた。本当なら勝手にどんどんしゃべってくれた方がありがたいのだけど、こういうときの坂本は本当に気が利かないのである。
「なにってべつに、世間話。進路の話とか」
「おまえが進路の話って」
「町山さん、東京の女子大いくから一浪覚悟してるみたいなこと言ってたよ」
な、に、そ、れ。
僕はそんなことまったく知らない。妙に親密な会話なのも気になる。打ちひしがれる僕は、坂本をさらに促す。
「ほかには?」
「なんだよ。もうないよ。あ、でも町山さんおまえのこと話してたよ」
「おい、ちょっと! ちょっとまてよ」
「マジで」
「うそだろ」
「うそじゃねえよ。文芸部のみんな、進路決まってるのすごいよねって。おまえも含めて、文芸部のみんな」坂本は円を描くように、人差し指を大きく回した。
「うわなんだそういうことか。いやでもすごいよ。くそーマジかよ」
「話しかけてこいよ」
と坂本が言った。
ん? と思う僕はまた黙り、坂本も黙り、ふたりで暗がりから町山さんの後ろ姿をじっと眺める。
どうしようかな。
僕はこの三年間で総計しても、かれこれ一分程度しか町山さんと言葉を交わしたことがない。「あ」とか「うん」とか「はい」「いいえ」くらいだ。彼女の瞳は色素が薄く、虹彩がくっきり見えることにも最近になって気がついたのだ。なにをどういう風に話していいのかがわからないという点で言えば、町山さんもサッカー部の清なんかと大して変わらないんじゃないかとすら思う。
「いや、やめておこう」
僕は言った。
「そりゃないよ、話しかければ意外としゃべってくれるって」
「そうかもしれないけど」と言う僕の気持は、意外と揺らいだりはしていない。
「ビビるなよ。どうせもう卒業なんだからいくらでも恥かき放題だろ。一組の川谷なんて今年に入って五人に告ってるらしいし、そんなのに比べたら話しかけるくらいなんてことないじゃん」
「え、川谷マジで?」
「マジらしいよ」
「今年に入って?」
「今年に入って」
「やば。まだ一ヶ月も経ってないじゃん。でもそういうことじゃないんだよ。だって、おれなんかが邪魔しちゃダメでしょ」
町山さん相手ならすぐわかることなのになあ、と僕はしみじみ思っていた。
「ああ」とつぶやいた坂本は、しばらくの沈黙をはさんで「なるほどね」と言った。
さっさと教室行こうぜ。そんで部室。僕が促せば坂本もついてきてくれる。
校舎内に入ってすぐに坂本が
「じゃあさっきおまえが言ってたこと、おれが今度町山さんに伝えればいいんじゃない?」
と言った。
「んん? それはどういうこと?」
「だからおまえが人知れずカッコつけてたことを、おれ経由で伝えたら町山さんおまえのこと好きになるかもよ」
「ばか! そんなわけあるか! 絶対やめろよ。言うなよ絶対」
「これもダメなのか」
「ダメだよ」
「もったいない。それくらい別にいいと思うけどな」
「ありがとう。でもそういうんじゃないよ。おれがめちゃくちゃカッコよかったって事実はおまえがずっと覚えておいてくれりゃ、それで充分だよ。それが本物だろ。違うか」
ぴゅ~と口笛を吹きながらウインクをする坂本。すごい生き物がいるもんだ、と僕は思う。
教室に戻って荷物をとる。
山之内の姿はもうないけど、まだ何人かが残って机に向かっている。もう二度と邪魔だけはしないぞ。そう思った直後、参考書から顔を上げた若本紅愛が「あ、安藤くん」と言うのでビビる。
「はい?」
「学ラン見つかった?」
「あー。実はまだなんだ」
すると彼女は立てた指を壁の方に向けながら、「なんかさっきね、安藤くんのこと探している人がいたよ。学ラン持ってた」
「え、うそ、どんな人?」
「誰だっけ。何組の人かは忘れたけど」
「男子?」
「そうそう、色白の」
「色白? もしかしてあの、すごい猫背の?」
「そうそう!」
福地じゃん。
お礼を言う僕に、よかったじゃん、と若本紅愛が表情を大きく崩すことなく小さく呟いてくれた。ひー、やべえ。僕はそのときの若本の遠のく顔、こちらを向く髪を束ねて露出したうなじに対して、体が震えるくらいの勢いで謝りたいと感じていた。「感謝」って字そのままの気持ちだ。若本の器に、僕は完全に飲まれてしまっていた。
「ありがとう」
こういうときの僕の声は小さくていけないのだが、若本紅愛は顔を上げ、ん? という顔をしたあと、ふわっと片手を上げた。とても律儀な感じのする、甲斐甲斐しい所作だったので、僕も同じようにした。
坂本と七組へと向かう。
福地の姿はない。
坂本も自分の荷物をとり、そのまま部室へと向かうことにした。
渡り廊下に出ると、空には月が浮かんでいた。照明塔の明かりに照らされた運動場は、夕日に染められていたときよりもずっと鮮明だ。
さみ~と言い合いながら部室棟へと駆け込む僕らは、卒業文集の話をする。浅野はもう出したぜ、と僕が言うと、坂本は「でしょうね」と言った。
「あとで読んでみ」
「はいはい」
「いや、よかったよ」
これはマジで。
部室の机には、僕の学ランが無造作に置かれていた。
感動から両手を合わせ膝をついていると、脚を組んだなっちゃんが「よかったね」と言った。「みんな優しくて」
ほんとにね。
「これは福地が?」
そう尋ねる僕に「ああ、あいつだよ」と久留米。帰ったのだろうか? 僕は加藤のマフラーと照本のカーディガンを丁寧にたたみ、リュックにしまったあと、久しく会った学ランに袖を通す。ポケットにはスマホがちゃんと入っていて、確認すると坂本の他に、中川からもラインが入っていた。
『見つかった?』
僕は早速返信する。
『お返事遅れました!学ランが無事見つかったことを報告いたします。ご協力ありがとうございました!』
もう後回しにはしない。ぼーっとするのもやめにする。この瞬間をできる限り覚えておかなければならない。
物事は更新されていく。
今日のあれこれも過去になる。
残るものも限られてくる。
みんなにも学ランが見つかった報告を入れていく。ああ、僕はちょっとだけ寂しい。嬉しいはずなのに、それを上回る喪失感に手を伸ばしそうになる。
僕はいまなにを失った? わからない。とにかく今日はもう終わる。終わるに足る理由を、僕は受け止めてしまった。あ、そのせいか?
しまった。
福地はまだそのへんにいるかもしれないとのことで、僕たちはみんなで部室をあとにする。月曜日は掃除しような! と念を押しながら。渡部先生が来るぞ。渡部先生が来る。バリトンボイスは憂鬱の調べだ。僕らはみんなで渡部先生のモノマネをした。久留米が一番うまかった。声の質が似ているのだ。
校舎の静寂を挑発するように、軽音楽部の音だけがはつらつと反響する廊下を歩いていると、なっちゃんが「安藤くん、遅れたけど」と言って、さっきの年賀状をくれる。あ、ありがとう。いま読んだほうがいい? 僕が尋ねると「あ、いや、帰ってから読んで。お互いのためにも」とのこと。
了解。
僕らは階段を降りる。ドアを開ける。強く冷たい風に吹かれ口々にさびーさびー言い合い、ちょっとだけ走ったり、立ち止まって誰かを待ったりする。ピロティーの太い柱を蹴り、白い息をチョップで割る。
「帰ったら書くか」
僕はそう呟くけど、マフラーに顔をうずめたなっちゃんがちらりと一瞥しただけで、坂本も久留米も反応をくれない。え、なんだよ。おまえらだってちゃんと書けよ。最後の文集なんだから、そこんところはよろしく頼むよ。
ポケットの中でスマホが振動する。取り出してみれば戸田セリナからで、『よかったね!』の一言。返信しなきゃ。中川とは違う言葉で。そう考えていると、校門へと続く道にある花壇のそばを歩いていたひとりの男子を見つける。ひどい猫背なのはいつものことだ。僕らに気づいたそいつは、胸の前まで手を挙げてみせる。
「福地!」
僕は声を張る。学ランありがとう! どこにあったの? 向こうはなにかを答えたけど、声量と、あと風のせいで、たったの一文字も届かなかった。それがなんだか楽しいような、名残惜しいような、とにかくじっとしていられない気持ちを喚起するので、僕はやつの声が届く距離まで小走りした。
まあ。
こんなもんでしょう。
それは、僕らが一緒に過ごした最後の金曜日だった。
~18:00