
「俺はだな別に乳首が見たいわけじゃないんだ。誰もが乳首を見たいみたいなそういう風潮が……」
と【部長】が早口で浴びせてくる言葉の意図するところが僕にはわかりません。なのに【部長】が嬉しそうに笑っているので、いっしょに笑ってしまった。これをミラーリングというらしい。相手と同じ仕草をしてみせることで、それがどういう効果を持つかは忘れた。いい意味だったと思う。人と人が接する上での摩擦を減らす、という点においてはとっておきの技術だとも思うし……ってそういう効果です。高校一年生である僕にとって、二コ上というのはそれだけ緊張を強いるモンスターだ。
「あれ。なんの話だった?」
と無神経な怪物がやや大仰に首をかしげ、斜め上に視線を向ける。
部室に来たらなぜか【部長】しかいなくて、いきなりグラビアアイドルの乳首の話をされた。僕はたぶん下ネタを話してもいいやつだと思われているのかもしれない。そもそも【部長】のいまの話は下ネタというか、公共の場に不相応な持論の開示? もっと笑った方がいいのか? 本音をいえば、笑うような話ではないと思っていた。無理に笑った後で急に「いまのはどこが面白かった?」と聞かれたら、絶対に答えられない。存在しない感情を説明することはできないからだ。普段の【部長】はどちらかというと堅物タイプで、過剰に場を律したがるというか、すぐ他人に注意したり高圧的に振る舞うことで威厳を保とうとするというか、そもそも雑談とかどうでもいい話を「どうでもいい話」だとすぐ指摘するような、そういう遊びのなさが人望にもつながっているような、そういう人が、いきなり乳首の話をするってどういう魂胆……万が一、その意外性を強く自覚してのことだったら、と考えて呼吸が震えた。一通り満足したのか手元の本に目を落としているが、結局最後まで話を聞いたところでなにを伝えたかったのか汲み取れなかった点も看過できない。【部長】がグラビアアイドルを好きかどうかも知らなければ(※そもそもどうでもいい)、なんならちょっと知りたくなかったくらいなのに、こういう側面もあるんだよ、みたいな含みがその様子から感じとれなくもない点もたいへん気分が悪く、終始脚を組んでいるその態度も許せない。度を超えているとすら思う。あと普段から部長に向いていないと思うことも多い。【部長】の部長観は古いと思っている。たぶん顧問の渡部先生あたりをリスペクトというかロールモデルにしているところがあるのかもしれないが、【部長】、そうはいかないんですよ。我々後輩とて、先生と二コ上では同じ態度はとれないんです。なのに僕らは先輩のロールプレイに付き合わされて日々ここ(※胸の奥)まで届くことのない三文パフォーマンスをぶつけられているのかと思うと結構……なかなかどうして。みんなもどう思っているのか聞いて回りたい。なのに今日に限ってなんで誰も来ないのだろう? テスト期間でもないのに。逆になんで【部長】は来ているのだろう? 受験勉強とかあるだろうに。難関大学とか目指して必死こけよ。あとさっきみたいな話をしておいてサッと黙るのはどういう了見? メガネがずり下がり、縁が瞳に重なっている。レンズも指紋だらけで、読書に支障が出かねないほど曇っている。そもそもなに読んでいるんだ。窓辺の一番いいポジションで脚を組んで読む本は、いったいなんなんだよ。
僕がパイプ椅子に座ったままぐっと深く腰を折ると、【部長】の手に収まった本の背表紙がチラリと見えた。
『娼年』
とあった。
お腹が痛いふりをして部室をあとにした。
どこにも居場所のなかった今年の四月、僕は図書館で本を読んで過ごしていた。そして違うクラスの菊池美和子さんに話しかけられ、ちょっとだけ話すようになり、文芸部の存在を知ったのだ。それから菊池さん目当てで文芸部に通ううち、彼女が【部長】と話すときだけやけに緊張し、そのくせ自分から積極的に話しかけることに気がついた。好意というものは、当事者ではない立場にこそ色濃く映るものなのかもしれない。
思い出すたび胸が苦しくなる。こんなこと思っちゃダメなのもわかっている。でもせっかくなら、負け方くらい選びたい。
なにもわからないぜ!
そういいながらポケットの中の大量のレシートを丸めてピロティー中央のゴミ箱へ投げたら一発で入った。
拍手の音が聞こえて振り返ると、巨大な柱のすぐ横に漫画研究会の後藤夏緒が立っていた。漫画研究会は文芸部と部室を共同で使っているので、個人的にはほとんど同じ部活の仲間みたいな感覚でいる。できるだけ垣根はないほうがいいとも思っている。
「ナイスピッチ安藤くん」
「うお、後藤さんかびっくりした」
「なっちゃんでいいよ」
ううーんと僕が唸っていると、彼女は足音を立てずに近づいてくる。
「これから部室?」
「あ、ちがうんだ。図書館行こうと思ってた。部室にはたぶんまだ【部長】いると思うけど」
「【部長】? 安藤くん、一回行ったんだ。ほかのひとは?」
「どうだろう。【部長】をひとりにしてあげようと出てきたところだから」
「そか」
「今日、暑いよね」と早々に会話をフェードアウトさせようとした僕だったが、後藤さんは「そういやごめん」という。「聞きたいことあったんだ」
「あ。【部長】に?」
「あ、ちがう」
「あ、僕に」
「そう。安藤くん。付き合ってる人とかいる?」
キィ───ンという音が聴こえたのであたりを見回してみたが、僕の耳の奥で鳴っているっぽかった。それが落ち着くまで、僕は右の耳を押さえながら結局黙ってしまう。
「え、なんかごめん。いいたくないならいい。大丈夫。クラスの人とどうなんだろうねって話になっただけだから」
そういって後藤さんは顔を左にかたむけ、肩をゆっくり回し始めた。ボキッと音がした。
「なんでぼく、え? ていうかそんな話に……なる?」
「うーん。でもなったんだ。そのクラスの子が文芸部とか漫画研究会って、彼氏彼女おる人おるん? って」と彼女は反対側の肩も同様に回し、ボキボキ……そのあとちょっと笑った。
「ああなんだ。やな感じのやつじゃん」
「やっぱそうだよね?」と後藤さんは眉をしかめる。「失礼だよね?」
「『おるん?』はナメてると思う」
「ちなみにわたしが安藤くんの名前出したわけじゃないよ。念のため。そのクラスの子がわたしに部員の名前を列挙させて、そいつは? って順にきいてきただけだから」
「そうなんだ。え? その人ちょっとこわいね」
「そう! わかる? 一部の人たちから悪魔って呼ばれてるけど」
「同じクラスに悪魔いるのやばいよ」
「ははは。たしかに。でもそっか。ごめんね答えさせちゃって。その人にも伝えとく」
「いいよ伝えなくて」
「だよね。やめとく」
「それがありがたい」
「話戻るけど安藤くんは【部長】苦手なんだっけ」
「いや、うーん、てか【部長】っていうより先輩全員そうかも。なんかスイッチバラバラだなって思うんだよね」
「スイッチ? とは」
「【部長】は先輩を敬え系のタイプでしょ? でもそういうのいいよって人もいるでしょ? で、そういうのいいよっていいながら実は気にしてる人もいるじゃん。どこにスイッチあるのか気になって疲れるときない?」
「なるほどね。難しいよね。わたしはもう【部長】を基準にしてる。一番面倒くさいから」
「おー。効率的」
「またひとつきいていい?」
「うん」
「さっきなにもわかんないぜっていってたよね。なにがわからないの?」
「いってないよ」
「ええ? いってたよ。わたし十分以内のことなら忘れないから」
「ははは」
「いや、ほんとだから」
「後藤さんさ、菊池さんっているでしょ?」
「菊池さんってあの……一瞬文芸部にいた」
「そうそう一瞬だけ」
「人の名前も忘れないから」
「ああ、うん、すごい。でその人が……」ちょっと待てよ? 【部長】のこと好きで文芸部に入ったってことは話していいんだっけ? 微妙だし、迷うくらいならいわないほうがいいのか。
「あの人の……なんていうの? すべてが」
「え?」後藤さんは額に手の甲を当てて固まった。
「だから、菊池さんのすべて」
「菊池さんのすべてがわからないってこと? え?」
「いやそう。まあ菊池さんに限らず他人全員そうだけど。わかんないもんだから。なにも」
「安藤くん、普段からそういうことよく考えるの?」
「別にそんなことはないけど、まあ、たまに。今日はたまたま菊池さんの番ってだけで。ほら、菊池さんでいうと例えば」
「なんで文芸部入ったんだろうとか?」
「そうそう、え。まさにそれ。すご」
「でもあれでしょ? 【部長】のことが好きだからじゃないの?」
「え? あ、そうなの?」
「菊池さん、部室で他の人いるまえで告白したじゃん、【部長】に」
「うそ!」
「あれ、知らない?」
「うそー!」
「……好きです! 付き合っていただけませんか! どうすれば付き合えますか! って」と後藤さんはやや高くて柔らかい声で菊池さんのモノマネをした。ちょっと似てた。「でも【部長】に断られちゃって、ね。辞めちゃったけど」
菊池さん、なんか最近顔出さないなーと思っていたら、菊池さん本人と廊下で鉢合わせて、向こうがちょっと気まずそうに顔を伏せ、小さな声で「おつかれ」といってきたのが最後のやりとりで、どういう経緯かなんて話の及ぶ隙すらなかった。
「ちなみに【部長】はなんていって断ってたの? てか断ったの?」
「うん。なんかほかに好きな人がいますって」
「へー。います? 丁寧語?」
きも。
「あ、そうそう。珍しいよね。たぶん【部長】も混乱してたんだと思う」
柔らかな風が吹いて、汗ばんだ肌がすこしだけひやりとした。あー、なんかいまの会話で色んな感情が刺激されて疲れたな、と思った僕は、図書館はやめにしてそのまま後藤さんといっしょに部室へ戻ることにする。荷物をすべて回収し、今日はもう帰ってしまおうという気分になったのだ。部室のドアを開けるとすでに【部長】の姿はなく、机の上にはその名残を示すかのように表紙を表にした『娼年』がそっと置かれていた。なんとなく手に取ってめくってみると、栞の挟まれたページが目に飛び込んでくる。性行為をせずにオーガズムに達することのできるおばあちゃんの場面だった。これは人間の可能性についての小説なのかもしれない。
「後藤さん、いまってなにか新しい漫画描いてる?」
パイプ椅子の背もたれにぎいいっと体重をのせた彼女は、「なっちゃんでいいよ」といって机の上でノートを開いた。質問に答えてもらえなかったのでやや狼狽したが、平静を装った。僕もなにかを書きたかった。日頃から、運動部のやつらが吠え面かくようなものを書けたら最高だなと思っている。でもどうせ運動部は小説なんか読まない。なんて思っていると意外と読んでいたり、意外と読んでいるもんだよなと思っているとやっぱり普通に全然読んでいなかったりするので、僕はこれからもできる限り物事を決めつけずに生きていけたらいいなと思う。ちなみに僕は次の小説で【部長】をモデルにした人物を登場させて、します。八つ裂きにな。
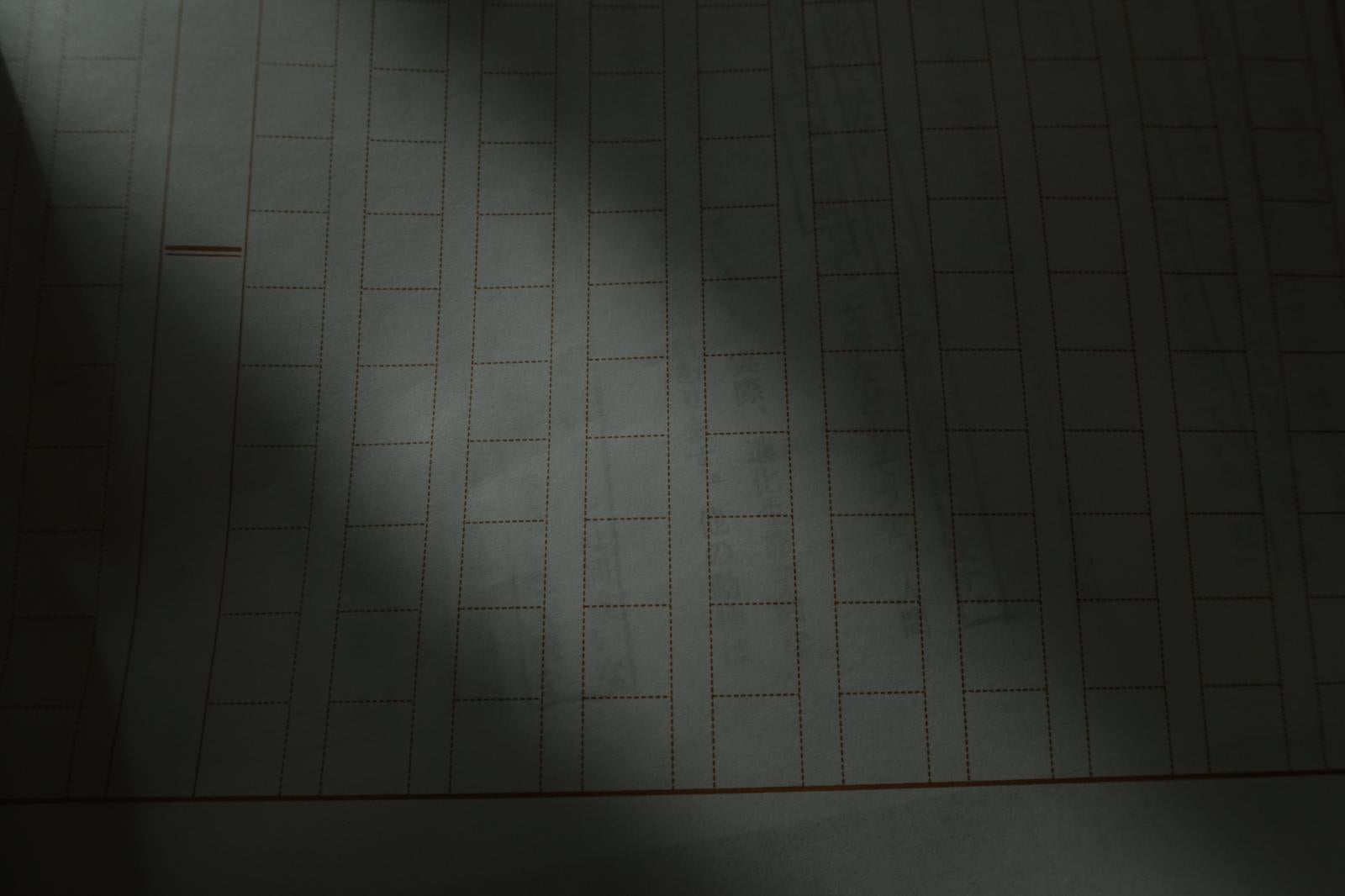
短篇集あります(Kindle Unlimitedで読み放題)↓
